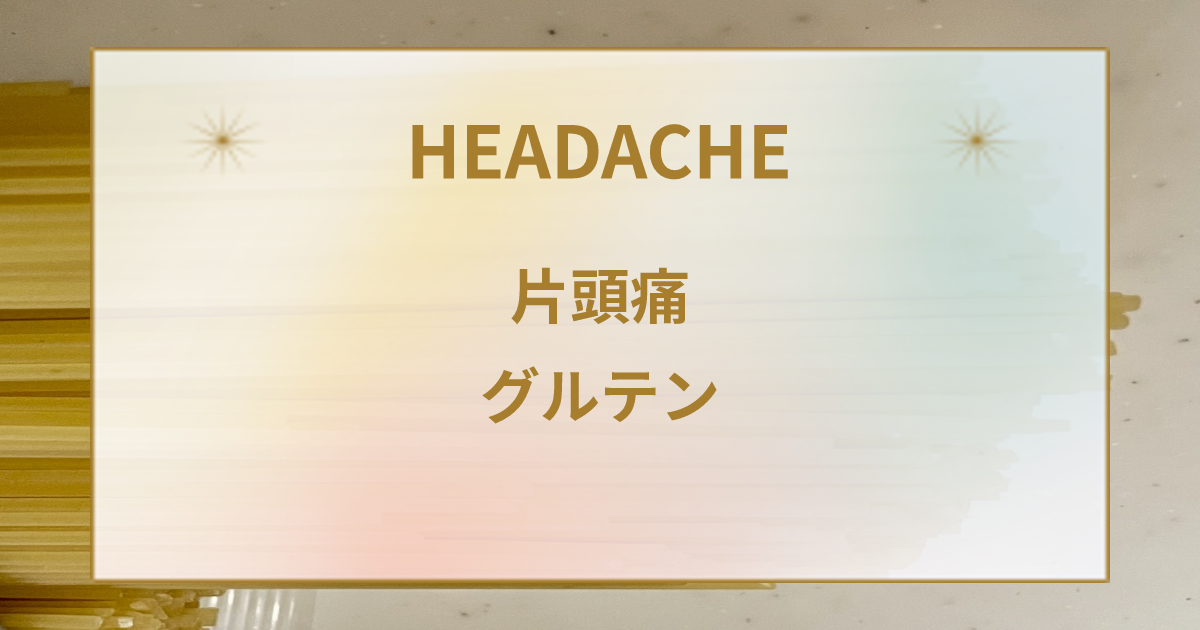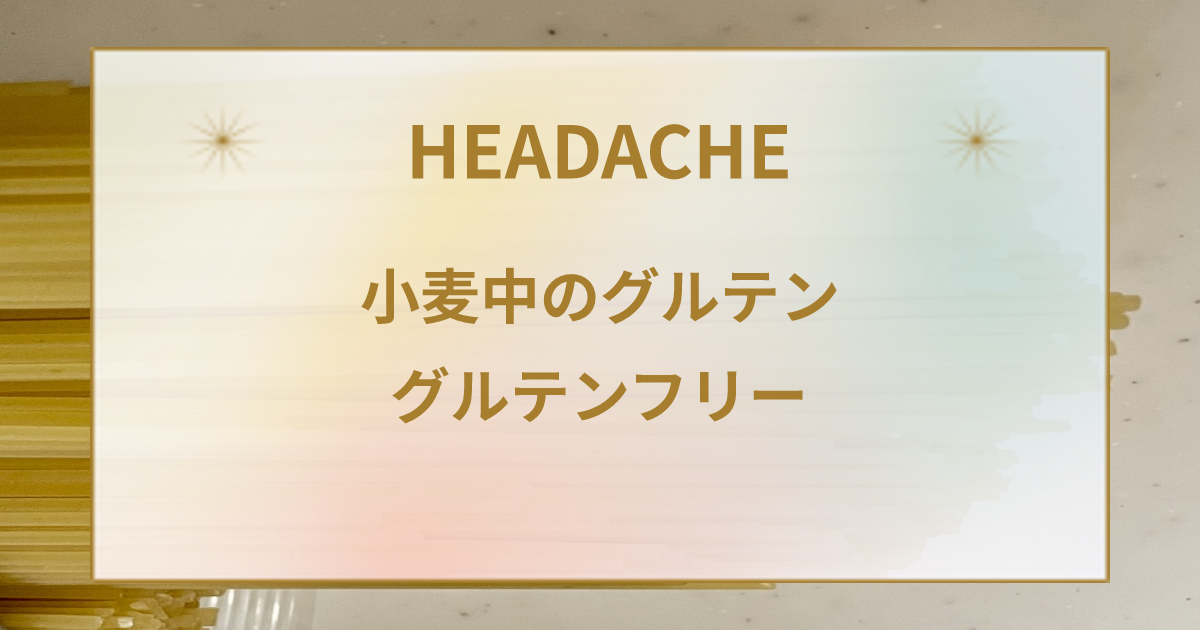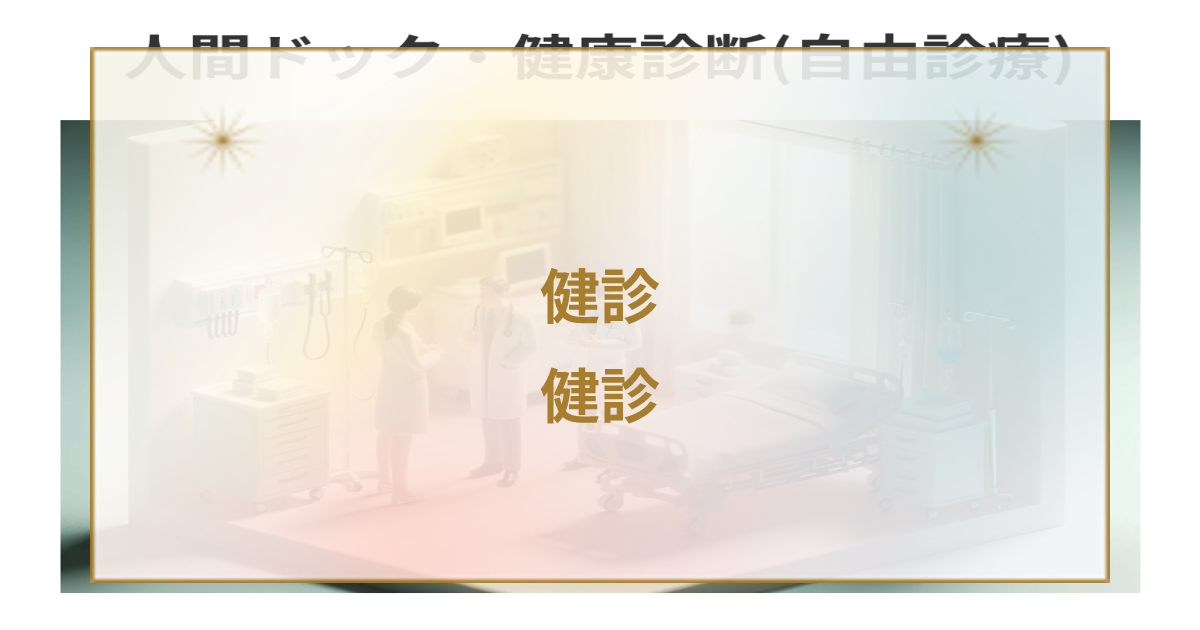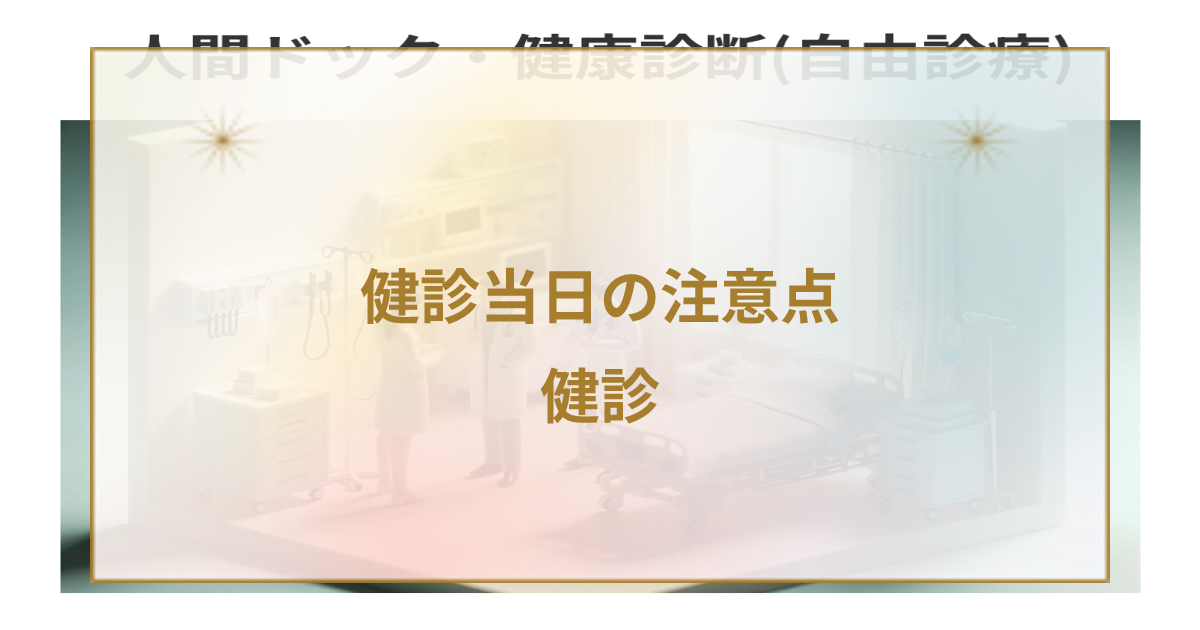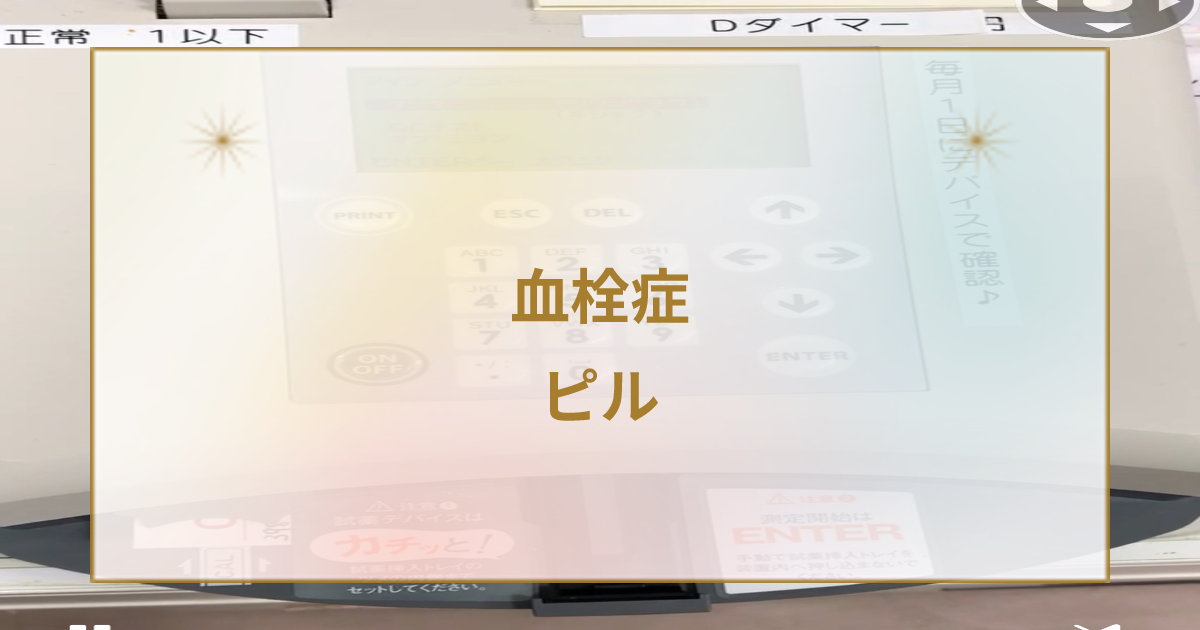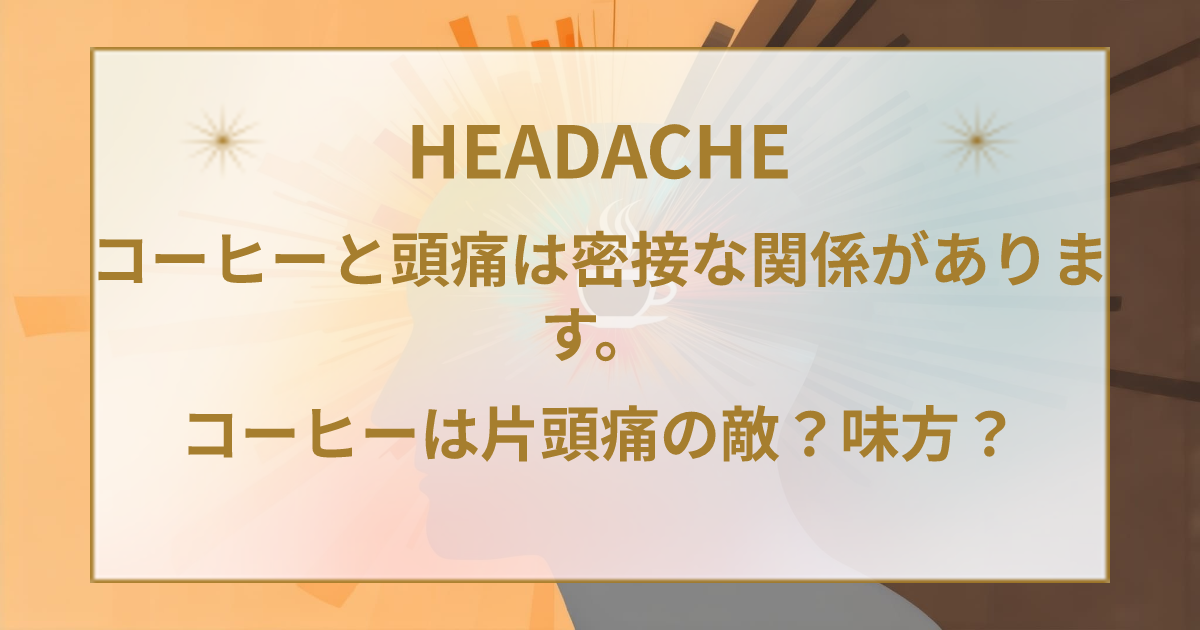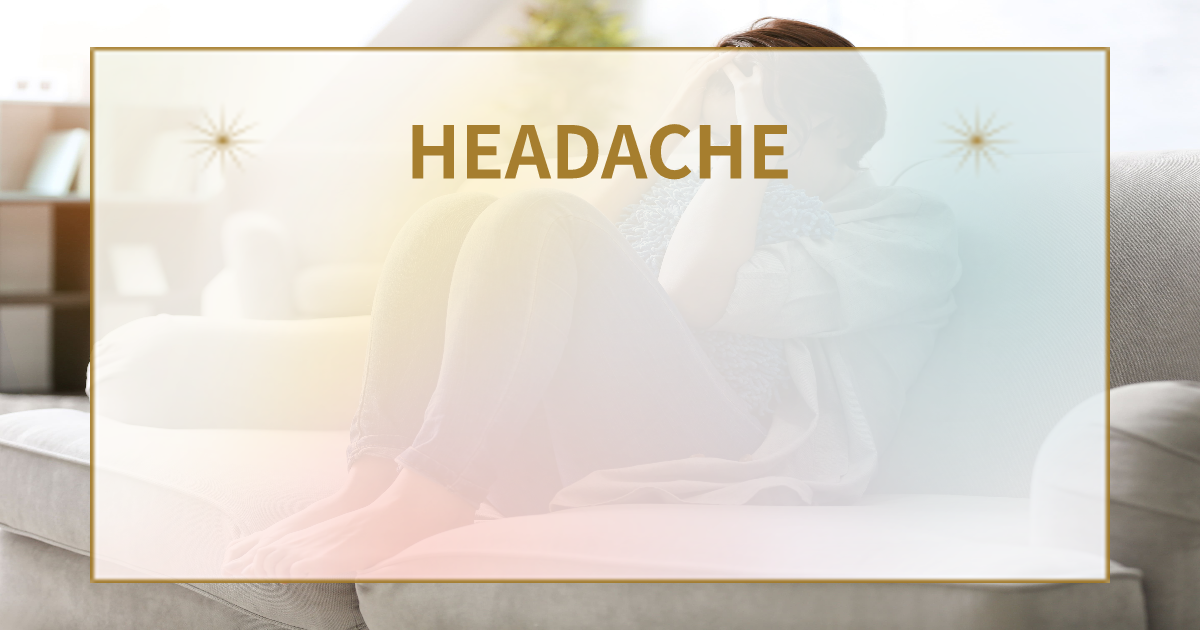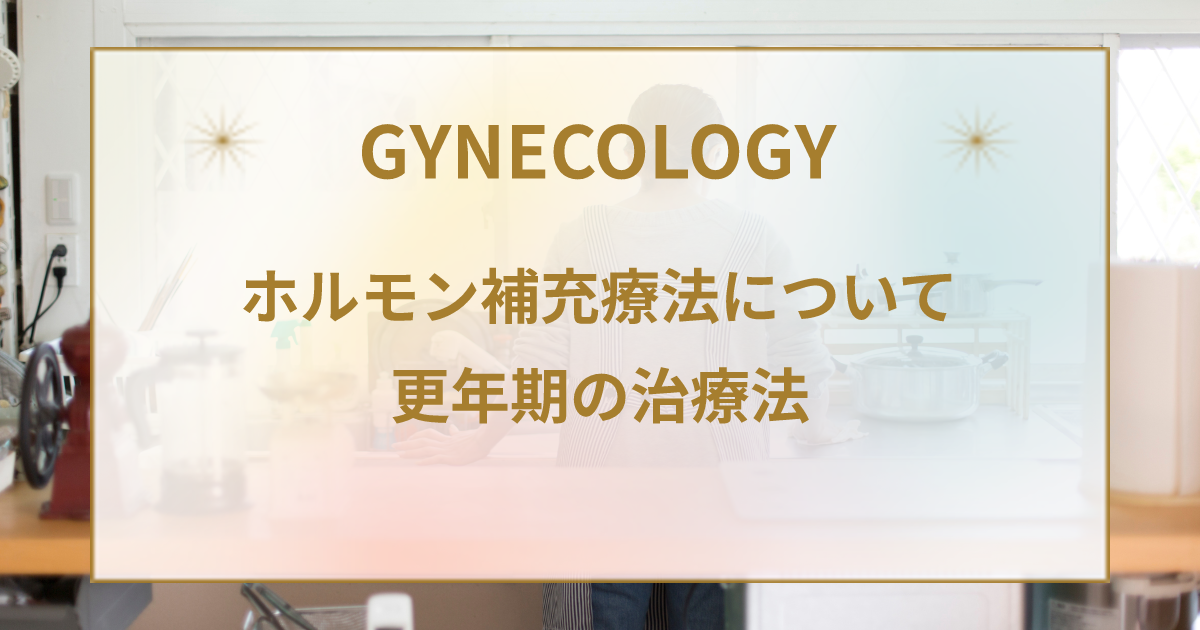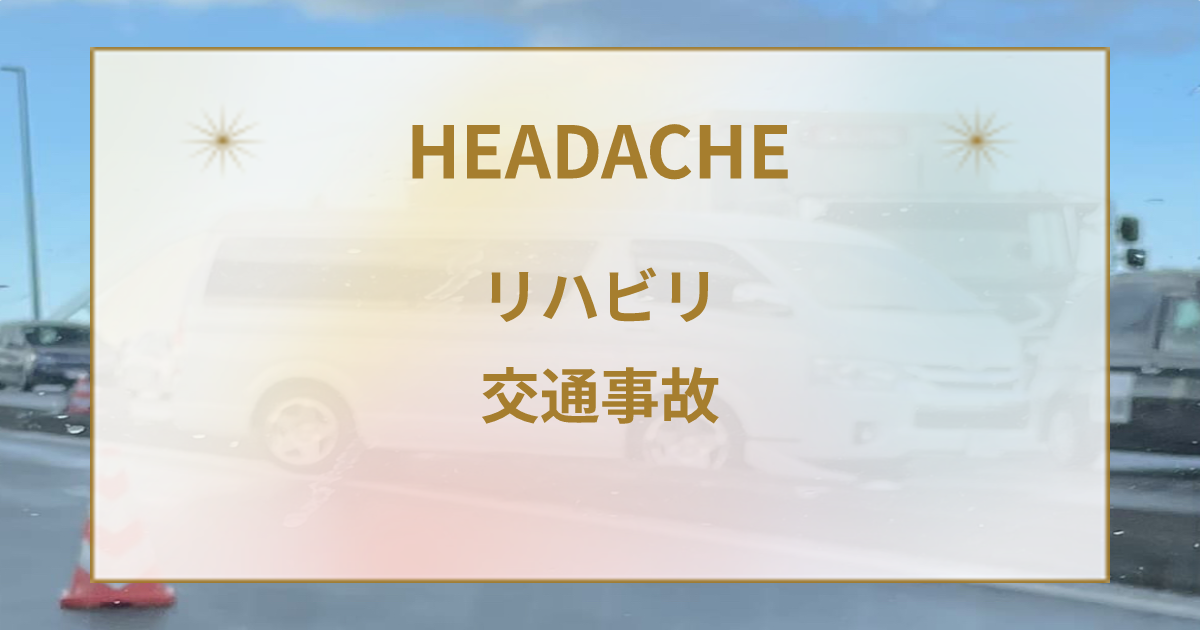
交通事故による腰痛
交通事故で負うケガの中に腰椎捻挫があります。衝撃により腰椎の周辺の筋肉・靭帯の損傷、椎間板や骨の損傷、神経の損傷や圧迫、仙腸関節(骨盤)の炎症や歪みを起こし、腰椎周りにダメージを受けた状態を指します。腰痛や痺れが発生します。
交通事故による腰痛は、直後から見られず時間が経ってから現れる事もあります。速やかに医療機関を受診し、リハビリテーションを開始することが重要です。
診断:X線やCT検査
治療:
・装具療法として、コルセットをつけ腰椎周りの安定性を高め、症状の緩和します。
・物理療法は遠赤外線・マイクロ波・低周波機器、温熱器などの機器・器具を用い、症状の緩和します。
・服薬は消炎鎮痛薬(NSAIDs)や筋弛緩薬などを使用し疼痛を軽減します。湿布を使用する事もあります。
・トリガーポイント注射はトリガーポイント(筋肉の硬結で、押すと痛み、関連痛を引き起こすツボ)に麻酔薬を注射します。